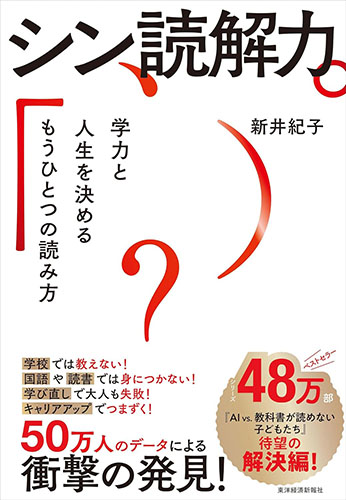「RSノート」は、シン読解力に的を絞って自学自習を進めるために、
非常に有効なツールであることが、相馬市などの取り組みから明らかになっています。
トレーニングの準備
| 児童・生徒が 使うもの |
|
|---|---|
| 先生が 準備する道具 |
|
まず用意するのは、市販の横書きのマス目のあるノートです。小学校の低学年は10マス、中学年は15マス、高学年以上は20マスを使うのがよいでしょう。
次に、RSTの受検結果の個票(受検結果に応じた学習アドバイスが載っている)を印刷し、切ってノートに貼ります。児童生徒には、このノートを使って1日10分程度の自学自習をさせ、その上で学習言語を意識しながら普段どおりの毎日の授業を受けさせます。
ただし、最初から児童生徒がRSノートに自力で取り組むのには困難がともないます。まずは、朝の帯学習の時間などを活用して、クラスで同じ内容に取り組み、徐々に自走できるようにサポートするのが良いでしょう。
トレーニングの
取り組み方法
ここでは、新井紀子『シン読解力』に載っている初級編トレーニングをもとに、どのようにRSのノートの取り組みをスタートできるか例を提示します。
題材として使うのは、理科、社会、算数・数学の教科書です。その日、授業のある教科を選び、1週間で3教科、取り組めるよう調整するようにしてください。週5日のうち残りの2日は、「筆算が確実にできる」ようにするなど目標をもって計算練習等をさせるのもよいでしょう。
低学年から取り組ませたい場合には、国語の教科書を使うこともできます。その日、トレーニングで取り組む箇所は、「前回授業で学んだばかりのところ」です。
小中学校では、授業は基本的に見開き2ページで進むので、①用語の定義が書いてあるところ、②難しい用語が登場するところ、③ぜひとも定着してほしいところ、から題材を選びます。小学校では担任の先生が「ここだけは読めてほしい」というところから厳選して視写箇所を決めてください。中学校以上の場合は、生徒に選ばせることもできます。
中学校では、その学年の教科を担当している先生が視写箇所を決め、前の週の終わりまでに担任の先生に伝達します。児童生徒が1分間に正確に視写する文字数の目安は、「学年×10文字」です。中学生は90秒で90字を目安にするとよいでしょう。
ただし、これはあくまで目安です。小学生は1分で、中学生は90秒で、何文字書けるようになりたいか、自分の目標をあらかじめ立てさせます。最初は、無茶な目標を立てる子がいますが、1週間(3回)やると自分のペースがわかるので、次の週には現実的な目標を立てられるようになります。こうして目標を自己調整することも、「自力で学ぶ」上ではぜひ身につけたい力です。
初級編シナリオ
- RSノート、筆記用具などを机上に出させ、ノートに日付と教科名を書かせる
- 視写させる提示文をスクリーンに表示し、それが書かれているページを「口頭で」伝える
- 児童生徒は、その指示を聞いて、さっと指定のページを開き、スクリーンに表示された提示し、文がどこに書かれているかを見つけ出させる
- 提示文を黙読させ、どんな内容だったかを思い出させる
- 提示文を音読させる
(ここで、漢字の読みがあやふやだったり、学習用語が定着していないなどを確認できる) - 改めて先生が手本の読みをし、正しい読み方を認識させる
- タイマーで時間を計って提示文を視写させる
- 時間が来たらストップさせ、書けたところに「 | 」のように区切りの印をつけさせる
- 30秒で区切りのよいところまで視写させる
- 隣の席の人とノートを交換し、間違っている箇所、字が汚な過ぎて判読できない箇所などに赤鉛筆で印をつけさせる
- 何文字書けたか「式を立てて」字数を数えさせる(例:15マスノートで「2行と5文字書いたが、2文字間違えた」場合は、「15×2+5-2=33、33字」)
- 視写が終わったら、ひとつだけ当該箇所の読解に関する質問をする
黙読→音読→聴読→視写→校閲という5つの異なる刺激を通じて、前回の授業の一番重要なところを読ませるというのが、このトレーニングの意図です。
こうしたトレーニングによって、知識ではなく、文を正確に読み解きできれば答えられるようになることが、シン読解力への第一歩となります。
加えて、①先生の指示を耳で聞き取る、②指定されたページを素早く開く、③指定された文を見開き2ページから素早く見つける、④学習用語の正しい読み方を復習する、⑤簡単な暗算、など授業の場面で必要になるスキルを、RSノート初級編で身に付けます。課題外在性認知負荷を下げることで、授業中に本丸の課題に十分なワーキングメモリを割けるようになり、授業の質が向上します。